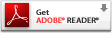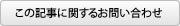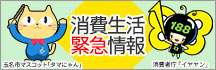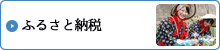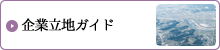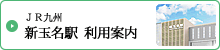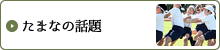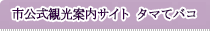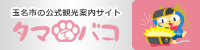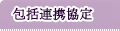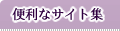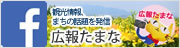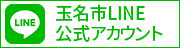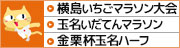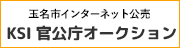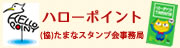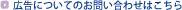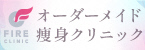15年ぶりに大浜外嶋住吉神社年紀祭が開催されました
令和7年5月2日から4日の3日間、大浜外嶋住吉神社年紀祭が執り行われました。この祭りは、五穀豊穣のほか、船の航海安全と豊漁を祈願するためのものといわれおり、ほぼ10年や20年おきに開催されます。
前回は平成22年に行われ、10年後の令和2年に行う予定でしたがコロナ禍のため延期となり、今回15年ぶりの開催となりました。特に最大の見せ場である「水上神事」には県内外から多くの人が見学に押し寄せました。
延久元年(1069)創建といわれる大浜外嶋住吉神社は、約一千年の間大浜町の産土神として人々の尊崇を集めてきました。創建の由来は次のように伝わっています。
創建の由来
延久元年(1069)、後三条天皇が住吉大神の神像を作らせ、「この神が霊験あらたかならいずれかの地にたどり着くであろう、そのときはどうかその地を鎮護なさってください」と祈り、帆も舵もない小舟に神像を乗せ摂津国の浪速の浦から流しました。
その小舟は大海原の荒波を凌ぎ、その年の仲冬(陰暦11月)15日に大浜の笠洲に漂着しました。そのとき、村人は沖の洲のあたりに夜ごとに光るものがあると皆怪しんで話し合っていましたが、そこに行ってみる者はいませんでした。ただ一人、白洲の浜の漁師 八郎が舟に乗りそこに行ってみたところ、神像を乗せた小舟を見つけました。八郎は小舟をひっぱって行こうとしましたが、重くて動かなかったので八郎はいよいよ不思議に思い、村に急ぎ帰って村の長老に報告しました。報告を受けた長老は、八郎や25人の村人と一緒に小舟の元に向かい、神像がどうしたいのか古式に倣って占ったところ、神像は村に上がりたいと思っていることが分かりました。そこで、仮の祠を建てて「浮舟大明神」とよんで神像を祀りました。
その後、この神像が住吉大神であることが分かり、このいわれを国主に告げ、延久2年(1070)に立派な神殿を建てました。延久3年(1071)に、阿蘇第一座の健磐龍命(たけいわたつのみこと)を勧請し、住吉大神と合わせて「外嶋大明神」として祀るようになりました。
祭りの内容
この大浜外嶋住吉神社の年紀祭は、住吉大神が流れついた場所に戻り、旅をして神社へ帰るという神事で、住吉大神を村へ祀った様子を再現していると伝わります。祭りの期間は昔は2週間もの長期にわたって行われていましたが、現在は3日間にわたり行われます。
1日目
砂引き神事が行われます。神像が漂着したといわれる笠洲に行き、早朝にまだ誰も足を踏み入れていない清い砂を持ち帰り、住吉神社境内と御旅所(おたびしょ、神像が漂着した笠洲に見立てた場所)に砂を敷き、清めるものです。
2日目
舟引き神事と米引き神事が行われます。舟引き神事は、白帆を立てた御神船を紅白に飾られた台車に乗せ、五色の梵天を振りかざしながら掛け声や謡にあわせて住吉神社まで進むもので、廻船模型を奉納する様子を再現していると考えられます。米引き神事は、大浜町の13各地区から奉納米を住吉神社へ寄進するためのものです。米俵を積んだ大八車を氏子総出で綱を引き、五色の梵天を振りかざしながら米挽音頭「ホーランエー、いちで祝いましょ、ヤハーエー」と謡いながら賑やかに進んでいきます。
3日目
水上神事を含む御神幸行列が行われます。住吉神社に鎮座する三神(注:1)を3基の神輿に遷し、神社から御旅所まで行列をつくり練り歩きます。御旅所で神事を執り行った後、水上神事(船渡御)を行います。
水上神事は、大浜の笠洲に漂着された住吉大神の神像を村へお迎えした当時の様子を氏子総出で再現したものです。3基の神輿をそれぞれ御座船(ござぶね)3艘に乗せます。1艘の御座船を3艘の櫂伝馬船(かいでんばせん)で曳いて、御旅所から大浜橋へ菊池川を遡ります。櫂伝馬船の舳先には「采振り(ざいふり)」、船尾には「剣櫂踊り(けんがいおどり)」と呼ばれる踊り手がおり、「ホーホエンヤ、ホーランエー、ヨイヤサノサッサ、ウントマカウントセ、ヨイヤサノサッサ」の謡と太鼓に合わせて、采振りと剣櫂踊りを披露します。謡と太鼓に合わせた漕ぎ手の櫂さばきと2つの踊りの一糸乱れぬ動きは、圧巻でこの祭りの大きな見どころのひとつです。
大浜橋のたもとに着いた神輿は御座船から降ろされ、今度は住吉神社に向かって行列をつくり進みます。住吉三神を神殿に戻し、感謝の意とこれからの加護を願って神事を執り行い、年紀祭を締めくくります。
住吉大神は海の神として信仰され、古くから航海関係者や漁民の間で霊験あらたかな神として崇敬されてきました。江戸時代、大浜町は年貢米などを大坂堂島(注2)へ積み出す外港として特に栄え、廻船問屋が軒を連ねており多くの人々が海や船に関係する仕事に従事していたと思われます。砂引き行事、米引き行事、御神幸行事と全てが大規模で、港町として栄えた大浜町の往時をしのばせるものがあります。
大浜外嶋住吉神社年紀祭米引き行事、御神幸行事(おおはまとしますみよしじんじゃねんきさいこめひきぎょうじ、ごしんこうぎょうじ)は、玉名市重要無形民俗文化財に指定され、また菊池川流域日本遺産の構成文化財にもなっています。
市役所2階文化課にて年紀祭のパンフレットを配布しております。ご入り用の方は、玉名市教育委員会文化課までお越しください。
注1:表筒男命(うわつつのおのみこと)、中筒男命(なかつつのおのみこと)、底筒男命(そこつつのおのみこと)の三神の総称を住吉大神(すみよしのおおみかみ)といいます。
注2:「大阪」の表記が一般的になる明治以前のことであるため「大坂」と表記しています。
カテゴリ内 他の記事
- 2026年1月30日 中央公民館(3月)講座開講のお知らせ
- 2025年12月10日 第55回玉名市公民館支館対抗駅伝大会の結果...
- 2025年9月11日 岱明地区支館ナイターソフトボール大会を開...
- 2025年7月4日 玉名市の地域学校協働活動の取り組みのご紹...
- 2025年4月23日 金栗杯玉名ハーフマラソン大会 大会結果
- 2026年2月5日 令和8年度玉名市ロビーコンサート出演者募...

- 2026年1月30日 春の装飾古墳一斉公開

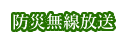






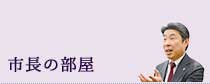
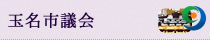
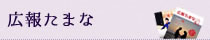
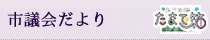
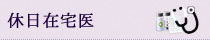

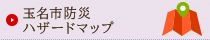
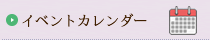
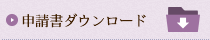
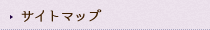
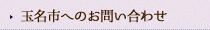
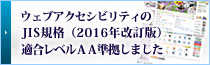
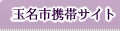

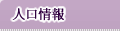



 このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。