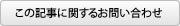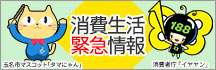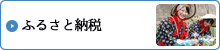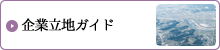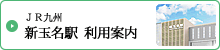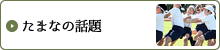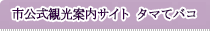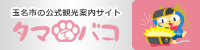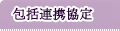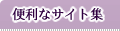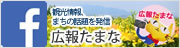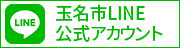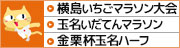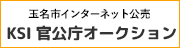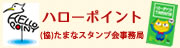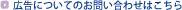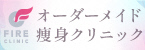廻船と高瀬御蔵の時代
菊池川の改修と干拓
菊池川の改修と干拓については、加藤清正による菊池川の流路変更とそれに伴う小田牟田・大野牟田新地の干拓が、天保3年(1832年)に書かれた鹿子木量平の「藤公遺業記」により知られていますが、清正の検地帳に見える田畑の増減や地名の変遷から、現在では、菊池川本流の流路変更は実際に行われておらず、菊池川の分流であり伊倉丹倍津を通り横島に流れていた旧唐人川を堰き止め、菊池川の川幅拡張と築堤工事を行い、中世期に自然陸化が進んで干潟(湿地)となっていた旧小田牟田・大野牟田を、開発により耕地にしたものと考えられています。
加藤清正の死後も子忠広による干拓が行われ、江戸時代には、藩や手永など干拓の主体も様々となり、目的も米の収量を増やすだけでなく、教育・土木・農業・貧民救済などの費用を捻出するためと多様化します。
「小田手永絵図」は玉名郡の小田手永を描いた絵図です。「手永」というのは肥後藩特有の言葉で、郡の下の数か町村から数十か町村をあわせた範囲です。菊池川絵図が製作された安政2年以降の絵図と思われ、部田見村の陣安次殿開(1796年)、御郡方開(1769年)、櫨方開(1758年)などが記載されています。
干拓は、干潮時を見計らって区域を分割して行われます。潮止口だけを残して堤防を築き、最後に潮止口に土のうを投げこんで一気に堰き止めるというやり方です。玉名平野の干拓は、以後明治・大正・昭和と続けられ、国営の横島干拓(昭和42年潮止め)を最後に現在の玉名平野が形作られました。
廻船と高瀬御蔵
 江戸時代高瀬には、菊池川流域でとれた年貢米を大坂堂島の藩の蔵へ運搬するための集積基地となった高瀬御蔵がありました。全国450万俵のうち40万俵を肥後米が占め、高瀬からはその半ばに当たる蔵米20万俵を始め、米・麦・大豆・小豆・菜種などの納屋物が積み出されました。また、大浜と晒はその外港として発展しました。高瀬御蔵は高瀬大橋より数百メートルほど下流の右岸一帯で、御蔵の付属施設である俵ころがしと渡頭(揚げ場)は現在でもその遺構が残っています。
江戸時代高瀬には、菊池川流域でとれた年貢米を大坂堂島の藩の蔵へ運搬するための集積基地となった高瀬御蔵がありました。全国450万俵のうち40万俵を肥後米が占め、高瀬からはその半ばに当たる蔵米20万俵を始め、米・麦・大豆・小豆・菜種などの納屋物が積み出されました。また、大浜と晒はその外港として発展しました。高瀬御蔵は高瀬大橋より数百メートルほど下流の右岸一帯で、御蔵の付属施設である俵ころがしと渡頭(揚げ場)は現在でもその遺構が残っています。
菊池川流域周辺から運ばれた米は、高瀬御蔵に運び込まれ、納入の量と品質がチェックされます。そして、米を御蔵から積み出す前に一時屋外の小高いところに積み上げますが、この場所を「御米山床」といいます。御蔵近くの民家の石垣には、御米山床を作ったときの碑が残っています。それから、平田舟で河口の晒浦まで運ばれ、そこから上荷船に積換えて沖に停泊している廻船まで運ばれます。その廻船で、数千俵単位の米が大坂まで運ばれるのです。御蔵の隣には、藩主の休泊施設であった高瀬御茶屋がありましたが、御蔵と共に明治10年の西南の役で焼失しました。
高瀬御蔵よりやや上流側には、菊池川に流れ込む用水路である裏川がながれ、その裏川に沿って高瀬町の商家が軒をつらねています。裏川からは、いくつかの階段が商家につながる小路に続いており、当時の商品運搬の様子が伺えます。
江戸時代の高瀬町の町並みに関しては、嘉永7年(1854年)に作られた高瀬町図が残っています。高瀬町は肥後五カ町の一つとして栄えますが、この絵図には、御蔵・御茶屋を始め、町奉行所・手永会所などの公的機関、寺社などが詳細に描かれています。
肥後の高瀬藩
寛文6年(1666年)、熊本藩主細川綱利の弟若狭守利重が、3万5千石を与えられ、江戸の鉄砲洲に居住します。これが、新田藩と呼ばれる肥後藩の支藩の始まりです。新田藩は、以後10代にわたって続きますが、明治元年、10代目利永の時、朝廷から利永に上京の命があり、利永はその命に従いますが、その後熊本に帰り本藩に服属することになります。この時、利永と家臣たちの居住地として選定されたのが高瀬の岩崎です。高瀬藩は明治元年に始まりますが、明治2年2月版籍奉還により本藩とともに廃止されます。
西南戦争と玉名
明治10年の西南戦争において、高瀬は、重要な位置を占めます。西南の役といえば田原坂の戦いが最大の激戦として有名ですが、薩軍本隊進攻の北限となったのが高瀬(玉名市)でした。高瀬の争奪を巡る官軍との激しい戦いに敗れ退いた薩軍が、吉次峠(玉東町)や田原坂(植木町)で決戦に臨んだのです。高瀬の戦いで、高瀬町の3分の1と周辺地域が兵火に遭いました。この間、官軍第14聯隊長乃木希典少佐の玉名村での負傷、薩軍1番大隊第1小隊長西郷小兵衛(西郷隆盛の末弟)の永徳寺での戦死、薩軍を応援した熊本最大の士族集団である熊本隊の寺田での激戦、下村(現玉名市下)での薩軍兵士の集団自決など様々な事象が伝えられています。
また、高瀬は、吉次峠・田原坂の戦いのときの兵站基地でもあり、征討総督有栖川宮熾仁親王の本営も置かれました。
カテゴリ内 他の記事
- 2017年11月14日 常設展示
- 2015年12月9日 日置氏全盛の時代
- 2022年7月16日 海外交易の時代
- 2026年1月15日 常設展「刀工集団・同田貫」

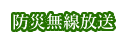






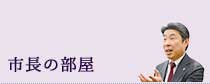
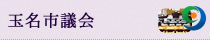
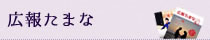
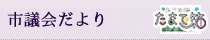
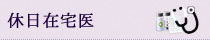

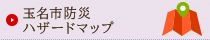
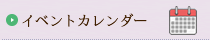
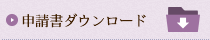
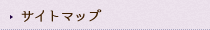
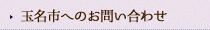
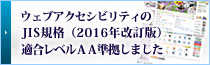
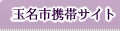

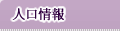

 このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。