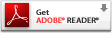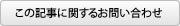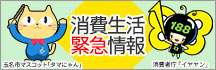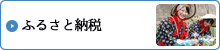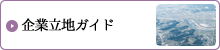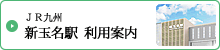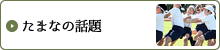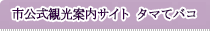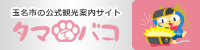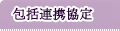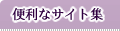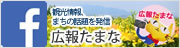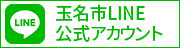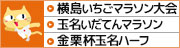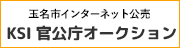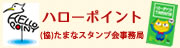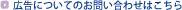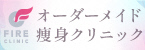菊池川流域日本遺産の紹介 第5回 条里跡、千年以上続く田園風景
米作り、二千年にわたる大地の記憶 〜菊池川流域「今昔『水稲』物語」〜
菊池川流域(玉名市・菊池市・山鹿市・和水町)は、2,000年前から現代に至るまでの米作りに関する有形文化財、祭りや食文化、文化的景観が残されている稀有な場所であるとして、平成29年4月に日本遺産の認定を受けました。
日本遺産とは、文化庁が平成27年度から開始した事業です。文化財保護法等による文化財保護制度とは異なり、指定文化財・未指定文化財の枠を超えた「我が国の文化伝統を語るストーリー」として観光などに活用し、地域活性化につなげていくことが目的です。
第5回 条里跡、千年以上続く田園風景
7世紀に入ると、隋に代わり中国大陸を統治した唐が高句麗への遠征を開始するなど、東アジアの国際関係が緊張状態になっていました。そのため朝鮮半島の国々や倭国(日本)では、中央集権的な国づくりが急がれました。倭国(日本)では天皇を中心とした国づくりを目指し、大宝元年(701年)に制定された大宝律令により、中央集権体制への方向性が示されました。
大宝律令では各個人・各家族単位で人々を管理し、税もその単位で賦課されました。税のうち、田んぼの収穫物の一部を国に納めるものが「租」と呼ばれ、田んぼの面積に応じて納める量が決まりました。田んぼの面積で納める量が決まるため、土地の管理が不可欠となり、「条里制」と呼ばれる土地区画制度が用いられました。
条里制とは、約109メートル四方の方形の土地区画を1坪とし、その坪が縦に6個分で1条、横に6個分で1里とした土地区画制度です。
菊池川流域の平地部分にも条里制による土地区画がいたるところに見られます。菊池市と山鹿市の菊池川本流沿いの平地や菊池川の支流である山鹿市の上内田川や岩野川沿いの平地がそれにあたります。玉名市においては、新玉名駅の南西側付近に条里制による土地区画がよく残っていると言われます。この一帯は玉名平野と呼ばれ、現在でも稲作が続けられており、この風景は「千年以上続く田園風景」といっても過言ではありません。
関連リーフレット
関連ホームページ
カテゴリ内 他の記事
- 2026年1月30日 日本遺産の日に伴う「玉名の日本遺産展」
- 2024年2月9日 菊池川流域日本遺産の紹介 第11回 菊池川...
- 2024年1月18日 菊池川流域日本遺産の紹介 第10回 菊池川...
- 2023年12月22日 菊池川流域日本遺産の紹介 第9回 米の食...
- 2023年12月12日 菊池川流域日本遺産カレンダーができました
- 2023年11月28日 菊池川流域日本遺産の紹介 第8回 菊池川...
- 2023年10月31日 菊池川流域日本遺産の紹介 第7回 五穀豊...

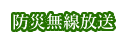






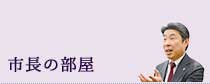
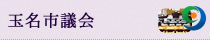
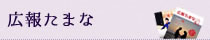
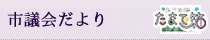
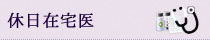

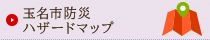
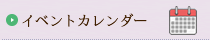
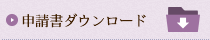
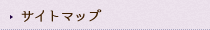
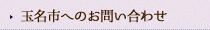
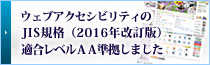
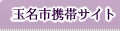

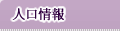
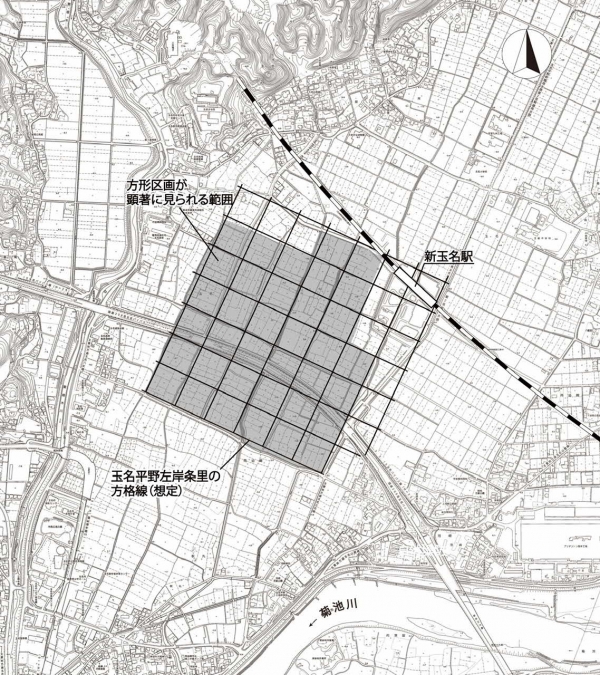
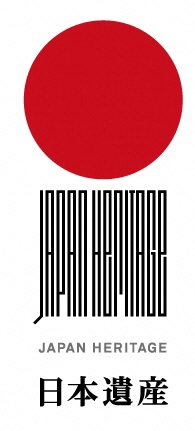

 このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。