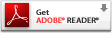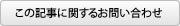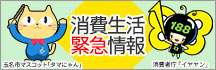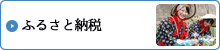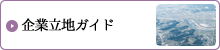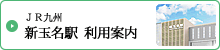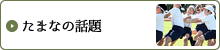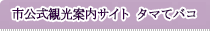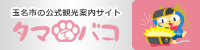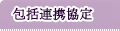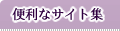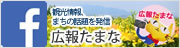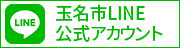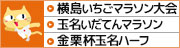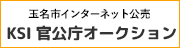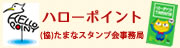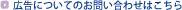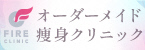防災コラム その8
玉名市防災コラム
今年6月〜9月にかけて、大阪北部地震、西日本豪雨、台風21号、北海道胆振東部地震など、立て続けに大災害に見舞われました。
こうした大災害によって、自宅に留まる避難(自宅待機)だけでは対応が難しくなるケースも多々あり、近隣の安全な場所や避難所への早期避難が必要になります。
第8回では、避難行動とは何か、また何を持って逃げればよいのかについて考えたいと思います。
第8回「災害時の避難行動と持ち出し品」
避難勧告等の対象とする避難行動については、これまで小・中学校の体育館などの指定避難所への避難が一般的でしたが、避難勧告等の対象とする避難行動については、指定避難所へ移動することだけではなく、次のすべての行動を命を守る避難行動と認識していただきたいと思います。
- 指定緊急避難場所への立退き避難
- 「近隣の安全な場所」(近隣のより安全な場所・建物等)への立退き避難
- 「屋内安全確保」(その時点に居る建物内において、より安全な部屋等への移動)
次に、避難する際に何を持って逃げるかについて説明いたします。非常時の持ち出し品については、常に持ち歩く品、災害時にすぐに持ち出す品、3日間程度の避難生活に備えた持ち出し品、避難生活が長くなりそうなときに必要な品の4つに分けることができます。
常時持ち出し品
外出中に被災することもあるため、常にバックやポケットに用意しておく品です。
飲料、携帯食、懐中電灯などのほか、スマートフォンの充電器や公衆電話で使用できる10円玉や100円玉なども役に立ちます。
災害後1日間をしのぐための持ち出し品
災害時にすぐ持ち出せる品、必要最低限の備えです。被災後の1日目をしのぐための品で、無いと困る品(例:常備薬、入れ歯、補聴器、離乳食など)をコンパクトにまとめておきます。リュックや背負える袋などに入れておくと、両手が使えて便利です。重い荷物を背負って避難するのは大変なため、できるだけ軽くしておき、すぐに持ち出せる場所に靴とセットでおいておくことが重要です。消防庁などのホームページで非常持ち出し品のチェックリストを確認し、自分に必要な品を確認しましょう。
災害後3日間程度の避難生活に備えた持ち出し品
避難した後、安全を確認して自宅に戻り、避難所へ持っていったり、自宅で避難生活を送る上で必要なもの(備蓄品)です。備蓄品については、第2回防災コラムも参照願います。また、衣類、タオル、歯ブラシ、災害用トイレなど避難生活を意識したものも役に立ちます。
避難生活が長くなりそうなときに必要な持ち出し品
避難生活が長期化しそうなときに、避難生活をより快適に過ごすためのものです。例えば、テント、寝袋、カセットコンロ、ランタンなどのアウトドア用品などがあります。
女性用品などの持ち出し品
避難生活には、女性ならではの悩みやストレスがでてきます。少しでもストレスが緩和できるよう、鏡、生理用品、おりものシート、マスク・ヘアゴム・化粧水・クレンジングシートなどの身支度用品、防犯ブザーや笛、自分の好きな香りグッズなどが役に立ちます。
小さな子どもがいる家庭などの持ち出し品
携帯用おまるや電池を使わないお気に入りのおもちゃ、おやつなどが役に立ちます。また、託児所や保育所など、保護者と一緒にいないときに災害にあったときのために、保護者の名前やアレルギーの情報が記載されたメモを持たせておくと役に立ちます。
今月のプラスアルファ
いざというときのスマートフォンアプリ
災害時に重宝するのがスマートフォンです。災害時に役に立つスマートフォンアプリを紹介します。
- ラジオアプリ:携帯ラジオを持ち歩けない場合に、スマートフォンで聴けるようにしておくと便利です。
- 災害情報アプリ:緊急地震速報や警報をプッシュ型で届けてくれるものもあります。
- 避難場所アプリ:土地勘のない外出先や旅先で近くの避難場所を探すのに利用できます。近くの避難場所まで案内してくれるものもあります。
- 位置情報を発信するアプリ:自分の居場所をあらかじめ登録した人に知らせてくれるアプリで、災害時の家族の居場所を知るために利用することもできます。
- SNSアプリ:友人知人とのコミュニケーションのほか、情報収集に利用できます。ただし、SNSの情報にはデマ情報も多いため、情報発信元をよく確認して、情報を利用してください。
- いのちを守るためのアプリ:応急手当の方法を確認できるアプリ、ライトの代わりになるアプリなど、被災時の危険から身をまもるためのアプリです。
モバイルバッテリーの備蓄
- スマートフォンは、外部との連絡や情報収集に便利なアイテムですが、電池が切れてしまうと何もできなくなります。9月の北海道胆振東部地震では、広範囲で発生した停電によってスマートフォンの充電のため、長い列ができました。
- 大規模な災害では3日程度停電が続くこともあるため、モバイルバッテリーを備蓄しておきましょう。自分のスマートフォンの容量を確認し、2〜3回程度は充電できる容量のモバイルバッテリーを用意しておきましょう。
- モバイルバッテリーは、使用していないときも放電して徐々に電池が減っていきます。定期的にチェックして、充電しておきましょう。
カテゴリ内 他の記事
- 2025年10月2日 大規模災害時における支援協力に関する協定...
- 2025年10月2日 災害発生時及び災害対応力強化における防災...
- 2025年9月5日 進化した3D防災マップで命を守る!「スマー...
- 2025年5月2日 危険なブロック塀などの除却費用を補助しま...
- 2024年8月13日 防災コラム その12
- 2024年6月26日 玉名市総合防災ハザードマップ及び指定避難...
- 2024年4月30日 玉名市総合防災ハザードマップが新しくなり...

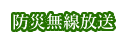






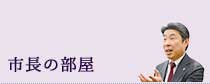
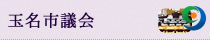
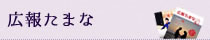
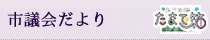
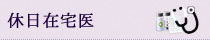

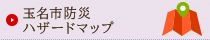
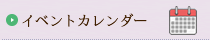
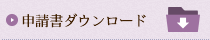
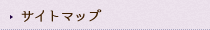
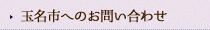
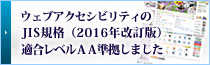
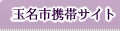

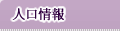
 このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。