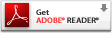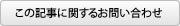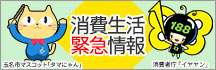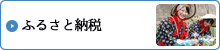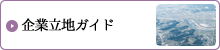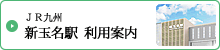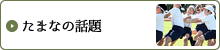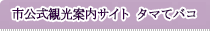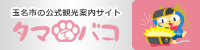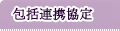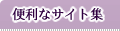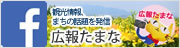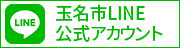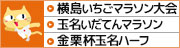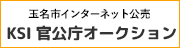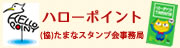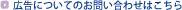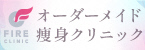【玉名の遺跡シリーズ13】玉名の舟形石棺
玉名市内の舟形石棺を紹介するリーフレットを作成しましたので、下記添付資料をご確認ください。
玉名地域は、舟形石棺の宝庫です。石棺は、この地域に豊富だった阿蘇溶結凝灰岩を切り出して、刳り抜いたり、加工しながら制作されました。そして、この地から有明海ー瀬戸内海を経由して、遠く岡山・愛媛・香川や大阪まで運ばれ、有力な古墳の棺として利用されていることがわかっています。
参考文献
高木恭二「菊池川流域の古墳」『国立歴史民俗博物館研究報告』第173集 2012
高木恭二「九州における舟形石棺」古代学協会発表資料集 1992
林田和人「刳抜式石棺からみた地域性と階層性」九州前方後円墳研究会資料集 2011
玉名市教育委員会「溝上地区の古墳群」『玉名市内遺跡調査報告書9』2017
玉名市教育委員会「後田古墳」『玉名市内遺跡調査報告書10』2018
後田古墳(玉名市石貫)
国指定史跡である石貫ナギノ横穴群がある丘陵上に位置しています。昭和25年頃に玉名高校考古学部によって調査され、石棺内から鉄剣、刀子などが出土しています。蓋の長さは1.56メートルで、やや長めの縄掛突起が付きます。蓋はかまぼこ型に近く、山下古墳石棺と同様に古いタイプとみられます。現在は竹林の中にあって見学は困難です。
経塚古墳(玉名市天水町) 熊本県指定史跡
天水町の丘陵上に位置し、県指定史跡「経塚・大塚古墳群」の一基です。昭和36年、ミカン畑造成中に発見され、その後、玉名女子高校によって発掘されています。内部から成人男性の全身骨格と共に外装付短剣、鉄剣、珠文鏡、管玉が出土しました。石棺蓋には方形区画の浮彫があり、縄掛突起が大きいのが特徴です。直径約45メートルの円墳ですが、前方後円墳の可能性も指摘されています。現在、覆屋の小窓から見学できますが、墳丘はミカン畑の中にあり、イノシシ除けの柵が設置してある場合があります。
大塚古墳(玉名市天水町) 熊本県指定史跡 石棺は復元して天水体育館へ移設
県指定史跡「経塚・大塚古墳群」の中心をなす前方後円墳(全長100メートル前後)です。主体部は2基の舟形石棺が埋葬されており、うち1基は盗掘を受けていましたが、鉄刀片、鉄剣片、鉄鏃、鉄斧などが残存していました。石棺は破損していたため、平成29年度に保存修復を行っています。その後、天水体育館の階段下に移設しているため、常時見学することができます。
宮の後古墳(玉名市溝上)
舟形石棺が最も多い溝上地区を代表する石棺です。円墳とされ、現在、直径約25メートルの墳丘が残存しています。盗掘によって蓋が割られている状態で、内部からは鉄剣、刀子、滑石製玉が出土したと記録されています。石棺の長さは2.34メートル、幅1.13メートルで、蓋は家形をしています。現在は、落葉などに埋もれていて見つけるのは困難かもしれません。
真福寺東古墳(玉名市溝上)
戦前の土砂採掘中に発見され、半分は破壊された状態で残存しています。石棺の長さは2.26メートル、幅1.06メートルで、内部から鉄剣片、滑石製玉、外部から鉄斧が出土したとの記録があります。棺材の一部は手前にも散財している状況です。北側にもう1基の真福寺西古墳(船形石棺)があったとされていますが消滅しています。
小路古墳(玉名市玉名) 市重要有形文化財 移設復元
昭和40年、山砂採掘中に偶然発見され、田添夏喜氏や玉名高校考古学部によって発掘されています。円墳とみられ直径11メートルが残存していました。単室の横穴式石室で、奥屍床に舟形石棺が置かれていました。石室内からは馬具、鉄鏃、装身具、須恵器などが出土しています。石棺としては最も新しく、墳丘に石棺が直葬されていたものが、石室内に安置されるという変化がわかる例です。現在、石室ごと移設復元されていますので見学可能です(誘導標識あり)。
カテゴリ内 他の記事
- 2025年12月25日 リーフレット「玉名の遺跡シリーズ」を配布...
- 2025年12月25日 玉名の遺跡シリーズ29「玉名の六地蔵」
- 2025年11月13日 玉名の遺跡シリーズ28「日嶽城跡」
- 2025年10月31日 発掘調査成果【玉名の遺跡シリーズ6】高瀬...
- 2025年10月10日 玉名の遺跡シリーズ27「柳町遺跡」
- 2025年9月5日 玉名の遺跡シリーズ26「高瀬本町通遺跡」
- 2025年8月8日 玉名の遺跡シリーズ25 「中世河口港関連遺...

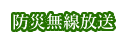






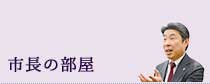
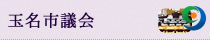
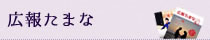
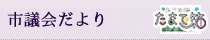
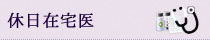

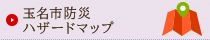
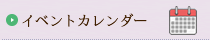
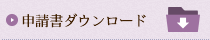
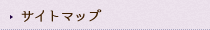
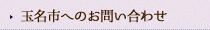
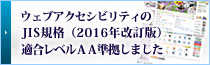
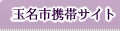

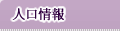


 このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。