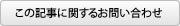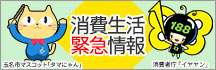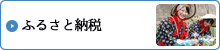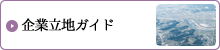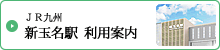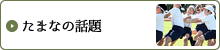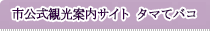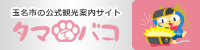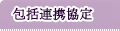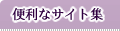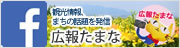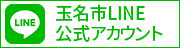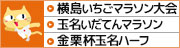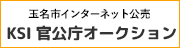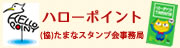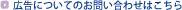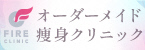【国民健康保険】マイナンバーカードを医療機関に提示することにより、ひとつの医療機関での窓口負担額が自己負担限度額までの支払いとなります
限度額適用認定証・標準負担額減額認定証とは
国民健康保険に加入している人が医療機関を受診したとき、かかった医療費の2割または3割を窓口で負担します。この窓口で負担する医療費が高額になったとき、事前に「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、ひとつの医療機関での支払いは定められた限度額(自己負担限度額)までとなります。
なお、限度額適用認定証を提示しない場合でも、後日申請いただくと自己負担限度額を超えた分を「高額療養費」として支給します。
また、世帯の所得によって、併せて入院時の食事代が減額される「標準負担額減額認定証」を発行いたします。併せて発行したものを「限度額適用・標準負担額減額認定証」といいます。
マイナ保険証が限度額適用認定証・標準負担額減額認定証として利用できます
健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)をお持ちの人は、医療機関等で本人が同意することにより、マイナ保険証が限度額適用認定証・標準負担額減額認定証として利用できます。
マイナ保険証の受付ができる医療機関・薬局でマイナ保険証を提示し、ご本人の情報提供に同意することで、限度額適用認定証・標準負担額減額認定証を提示したことになります。
また、国民健康保険加入者のマイナ保険証情報は自動で更新されるため、限度額適用認定証・標準負担額減額認定証を毎年申請していただく必要はありません。
注意点
- マイナンバーカードリーダーが設置されていない医療機関・薬局ではご利用できません。
- 国民健康保険税に滞納がある世帯の場合は利用できない場合があります。
- 直近12カ月の入院日数が90日を超える(長期該当)住民税非課税世帯の人が、入院時の食事療養費の減額をさらに受ける場合は、別途申請が必要です。
マイナ保険証をお持ちでない人は
事前に、医療機関での支払いが限度額までとなる「限度額適用認定証」(所得によっては、併せて、入院時の食事代が安くなる「標準負担額減額認定証」)の申請が必要となります。
申請月の初日から適用され、資格確認書の有効期限と同じ7月末(満70歳の誕生日前の場合は7月末でない場合もあります。)まで有効です。
注意点
- 月をまたいだ申請とならないようご注意ください。(例:9月10日から入院したため9月1日から有効な限度額適用認定証・標準負担額減額認定証が必要だったが、10月5日に申請するなど)
すでに限度額適用認定証・標準負担額減額認定証を持っている人が、8月以降も継続が必要な場合は、7月下旬から更新申請を受け付けますので、8月末までに手続きをしてください。
- 入院や手術の具体的な予定がなくても申請することができます。
- 手数料はかかりません。
- 適用区分に関するお電話でのお問い合わせにはお答えできません。ご了承ください。
申請時に必要なもの
- 申請者の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 対象者の資格確認書
- 別世帯の人が申請される場合は、対象者の資格確認書をご持参いただくか、委任状が必要です。
申請先
玉名市役所保険年金課または各支所市民生活課
交付の対象となる人
| 0歳から69歳までの人 | 70歳から74歳までの人 | |
|---|---|---|
| 交付の対象となる条件 |
|
|
(注)国民健康保険税を滞納されており、交付できない場合は、窓口で3割(または年齢や所得等により2割)負担した後、高額療養費の支給申請を行ってもらいますが、支給に当たっては滞納されている国民健康保険税へ充当をお願いします。
自己負担限度額について
高額療養費の対象となる自己負担限度額は「70歳未満の人」と「70歳以上75歳未満の人」で異なります。また、世帯の所得に応じた負担になるよう自己負担限度額が設定されています。
入院時の食事代や保険対象外となる差額ベット代などは支給の対象外となります。
70歳未満の方
区分名 (注1) | 所得区分 | 自己負担限度額 (月単位) | 食事代 (1食当たり) R7.4.1〜 |
|---|---|---|---|
| ア | 基礎控除後の所得が | 252,600円+(医療費-842,000円)× 1 % <140,100円> | 510円 |
| イ | 基礎控除後の所得が 901万円以下の世帯 | 167,400円+(医療費-558,000円)× <93,000円> | |
| ウ | 基礎控除後の所得が 600万円以下の世帯 | 80,100円+(医療費-267,000円)× <44,400円> | |
| エ | 住民税非課税世帯を除き | 57,600円 <44,400円> | |
オ (注2) | 住民税非課税世帯 | 35,400円 <24,600円> | 240円 (91日以上190円) |
(注)< >は「多数該当」といい、過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当する場合の限度額です。
(注1)70歳未満の方については、すべての所得区分で「限度額適用認定証」を発行します。
(注2)区分オの方は、入院時の食事代が安くなる「標準負担額減額認定証」を併せて発行します。(併せて発行したものを「限度額適用・標準負担額減額認定証」といいます。)
また、過去12か月以内で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の認定を受けていた期間の入院日数が90日を超える場合は「長期入院」該当となり、食事代がさらに減額されますので、「長期該当認定申請」をご参照いただきお手続きをお願いします。
70歳以上75歳未満の方
区分名 | 所得区分 | 自己負担限度額 (月単位) | 食事代 (1食当たり) R7.4.1〜 | |
|---|---|---|---|---|
外来 (個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) | |||
現役並み所得者3(注4) | 基礎控除後の所得が 690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円> | 510円 | |
| 現役並み所得者2 | 基礎控除後の所得が 380万円以上690万円未満 | 167,400+(医療費-558,000円)×1% <93,000円> | ||
| 現役並み所得者1 | 基礎控除後の所得が 145万円以上380万円未満 | 80,100円+(医療費‐267,000円)×1% <44,400円> | ||
| 一般(注4) | 基礎控除後の所得が 145万円未満等 | 18,000円 (年間上限 144,000円) | 57,600円 <44,400円>
| |
低所得者2 (注5) |
住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 | 240円 (91日以上190円) |
低所得者1 (注5) | 8,000円 | 15,000円 | 110円 | |
(注)< >は「多数該当」といい、過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当する場合の限度額です。
(注4)「現役並み所得者3」及び「一般」の区分では、限度額適用認定証が発行されません。
(注5) 区分「低所得者2」と「低所得者1」の人には、入院時の食事代が安くなる「標準負担額減額認定証」を併せて発行します。(併せて発行したものを「限度額適用・標準負担額減額認定証」といいます。)
また、「低所得者2」の区分で過去12か月以内で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の認定を受けていた期間の入院日数が90日を超える場合は「長期入院」該当となり、食事代がさらに減額されますので、「長期該当認定申請」をご参照いただきお手続きをお願いします。
現役並み所得者
同一世帯の課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人。ただし、課税所得が145万円以上であっても、下表にあてはまる場合は、「一般」の区分となります。
同一世帯の70歳以上 | 収入 |
|---|---|
| 1人 | 383万円未満 |
| 2人以上 | 合計520万円未満 |
同一世帯の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者が1人の世帯でも、同一世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した人がいる場合は、その人を含めて対象者が2人以上の基準で判定することができます。
低所得者2
国民健康保険被保険者全員と世帯主が住民税非課税の世帯に属する人(低所得者1以外の人)
低所得者1
国民健康保険被保険者全員と世帯主が住民税非課税で、かつ各種所得等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる人
長期該当認定申請
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の認定を受けられる入院が、過去12か月以内に90日を超えた場合(以下「長期該当」という。)で、区分オと低所得者2の方は、申請を行うことで1食あたり190円に減額となります。
この長期該当は、申請月の翌月初日を長期該当認定日とします。(すでに長期該当の認定を受けている方で、8月1日以降も継続して長期に該当される人については、8月末日までの申請の場合のみ8月1日を長期該当認定日とします。)
長期該当認定申請に必要なもの
- 申請者の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 現在お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証
- 申請月以前の12カ月以内で90日を超える入院があったことがわかる領収書
- 別世帯の方が申請される場合は、対象者の資格確認書をご持参いただくか、委任状が必要です。
標準負担額差額支給申請
長期該当認定申請日から長期該当認定日の前日までに入院があった場合、申請を行うことにより当該入院食事療養にかかる標準負担額の減額について差額を支給します。
標準負担額減額差額支給申請に必要なもの
- 申請月の食事代が分かる領収書
- 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
- 申請者の身元が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 別世帯の方が申請または、世帯主以外の口座に振込を希望される場合は委任状が必要です。
委任状
委任状はこちらのリンクからご確認ください。
カテゴリ内 他の記事
- 2025年8月7日 【国民健康保険】特定疾病療養受療証につい...
- 2025年8月6日 【国民健康保険】出産育児一時金
- 2025年7月31日 葬祭費の支給(国民健康保険・後期高齢者医...
- 2025年7月29日 【国民健康保険】高額療養費の支給(償還払...
- 2025年7月24日 【国民健康保険】療養費の支給について
- 2025年7月22日 療養の給付
- 2021年4月12日 【国民健康保険】小児弱視等の治療用眼鏡を...

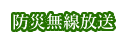






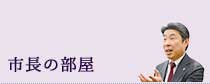
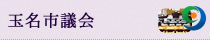
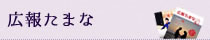
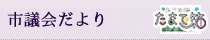
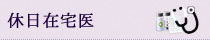

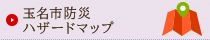
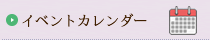
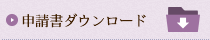
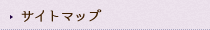
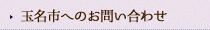
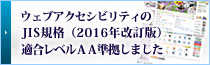
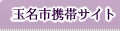

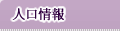
 このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。