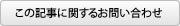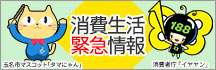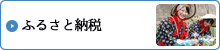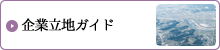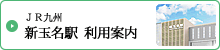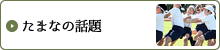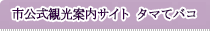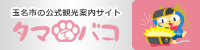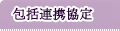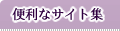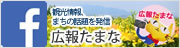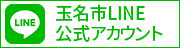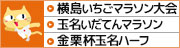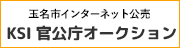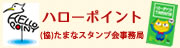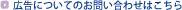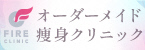開田筥崎八旙宮王面 附 掛額
開田筥崎八旙宮王面 附 掛額(ひらきだはこざきはちまんぐうおうめん つけたり かけがく)
【種別】玉名市指定重要有形文化財(工芸品)
【員数】王面 三面、掛額 一面
【指定年月日】平成20年12月22日
【所在地】―
【所有者】民間団体
【内容・特徴】
開田筥崎八旙宮王面は、三面揃った例としては熊本県内出は最古の部類に属します。三面全てが樟材で製作されており、内面に「紀吉満作」「末藤什物」と銘が入っています。
赤で彩色された火王面は口を大きく開いた阿形に作られ、鼻先は失われています。緑で彩色された水王面は口を結んだ吽形に作られています。風王面は薄い朱色で彩色されており、鼻先を失っています。吽形に作られていますが、口角を下げて口を結んだ水王面とは異なり、風王面は口角を上げて口を食いしばっています。
王面は鉾の先などにつけて神幸行列を先導したり、神殿の柱に懸けて「魔よけ」としたため、目鼻は開いていません。目鼻を開けない火王・水王面の例は、古いものでは14世紀半ば頃のものがあります。特に南九州に多く分布しており、ある時期から風王の面が加わります。その初期ははっきりしませんが、時代が判明する例としては熊本県山鹿市大宮神社の寛文2年(1662年)のものがあります。開田筥崎八旙宮の王面は、その作風の特徴が鎌倉時代の作例に顕著に見られることから、それよりも古い14世紀から15世紀前半頃の作と考えられます。
掛額は淺山平太夫が寛文7年(1667年)に奉納しています。淺山平太夫は現在の熊本県八代郡氷川町の一部に知行地300石を領していた人物で、肥後藩主細川綱利の御腰物拵奉行(藩主の佩刀や装身具を取り扱う役職)を務めていました。
カテゴリ内 他の記事
- 2026年1月9日 六地蔵板碑(天水町野部田)
- 2026年1月7日 永仁二年銘宝塔
- 2025年12月26日 小路古墳石室・舟形石棺 附 出土品一括
- 2025年12月25日 一ニ三之橋架橋碑
- 2025年8月29日 関白塔 附 浄光寺跡出土五輪塔地輪
- 2025年3月31日 木造阿弥陀如来立像及び厨子・添状
- 2025年3月31日 鹿子木文書

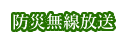






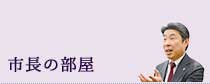
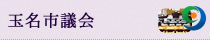
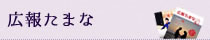
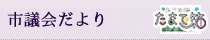
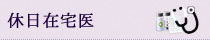

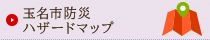
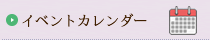
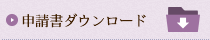
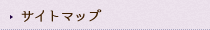
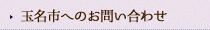
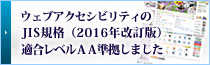
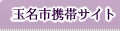

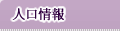
 このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。