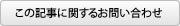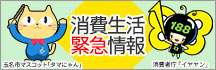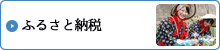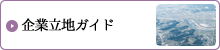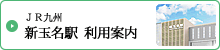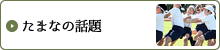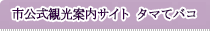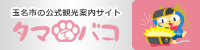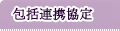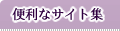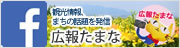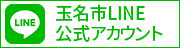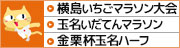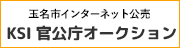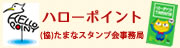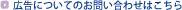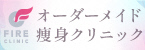木造男神坐像
木造男神坐像(もくぞうだんしんざぞう)
- 員数 1躯
- 指定年月日 平成29年7月18日
- 所在地 玉名市立歴史博物館こころピア(寄託)
- 寄託期間 平成28年12月27日〜平成33年3月31日
- 所有者 玉名大神宮
木造男神坐像は、玉名大神宮東末社の社殿に安置されていましたが、現在は保存のために玉名市立歴史博物館こころピアに寄託されています。
平安時代に確立された、一材から全体を彫り出す一木造り(いちぼくづくり)という技法で作られています。素材は榧(かや)とみられ、像の高さは70.0センチメートルです。冠の形状、表情や体部を抽象的に表す表現技法などから、平安時代後期(12世紀)頃の典型的な作と考えられています。平安時代の神像は確認例が少なく、旧玉名郡内では荒尾市の野原八幡宮の木造僧形神(応神天皇)坐像・木造女神(神宮皇后)坐像、玉東町の稲佐熊野座神社の木造女神像に続き4例目になる貴重なものです。
怒りの表情を表し、座して両手を胸に構え笏(現在は欠失)を持つ姿に作られています。
通常は木心が中央にくるように木取りを行いますが、本像は左肩付近にもってきています。さらに、左胸に枝跡があるため、彫刻しやすい良材ではありません。冠の上部に大きな割れがあり、別材を挟み込んでいることから、落雷で割れた御神木に神性や霊性を見出し、あえてそうした部材を用いた可能性があります。また、左胸に枝跡がくるような木取りを行っていることにも何らかの意図があった可能性は否定できません。
玉名大神宮の創建は『日本書紀』の記述では、景行天皇が土地の豪族土蜘蛛を討伐した際に遥拝宮を造り、天照大神の神助を乞うたことに由来するとされ、天照大神のほか、景行天皇、阿蘇四神、菊池則隆、玉依姫、菊池一族の男女が祭神として祀られています。本像は菊池則隆像との伝承もありますが、今のところ、それを肯定する史料も否定する史料も見つかっていません。
玉名大神宮の所在する地は、中世には仁和寺仏母院領でした。仁和寺仏母院領玉名荘は平安時代最末期〜鎌倉時代初期に山鹿荘から分割されて成立しており、本像はその頃に製作されています。しかし、玉名荘や玉名大神宮についての拠るべき史料は少なく、そのような中で、本像のような表現や技法から時代の指標となりうる具体的な遺品の存在は、玉名地域や玉名大神宮の歴史を探る大きな手掛かりとなるものです。
カテゴリ内 他の記事
- 2026年1月9日 六地蔵板碑(天水町野部田)
- 2026年1月7日 永仁二年銘宝塔
- 2025年12月26日 小路古墳石室・舟形石棺 附 出土品一括
- 2025年12月25日 一ニ三之橋架橋碑
- 2025年8月29日 関白塔 附 浄光寺跡出土五輪塔地輪
- 2025年3月31日 木造阿弥陀如来立像及び厨子・添状
- 2025年3月31日 鹿子木文書

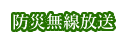






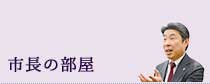
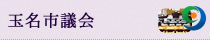
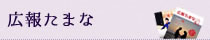
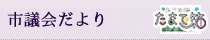
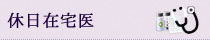

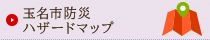
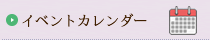
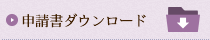
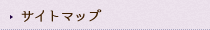
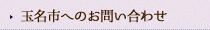
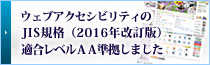
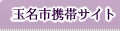

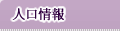
 このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。