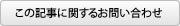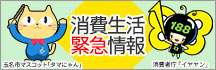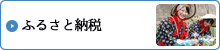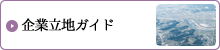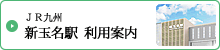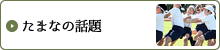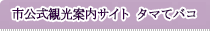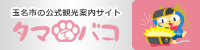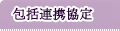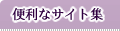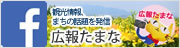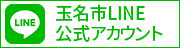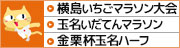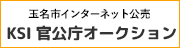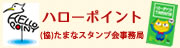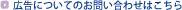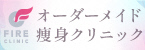企画展 「たまな発掘速報展」
国道208号線玉名バイパス建設や開発などに伴い菊池川下流域で行われた発掘調査の成果を企画展で紹介しました。
縄文時代 1上小田宮の前遺跡(玉名市上小田)
菊池川左岸の水田地帯にあります。縄文時代後晩期から中世にかけての生活のあとが発見されました。水田の真下2メートルのところにあった縄文時代の自然流路からは県内最古の弓、溝のある砥石、頭や手足が欠かれた土偶、ドングリを煮て焼き付いた土器などが出土しています。玉名平野において縄文時代の人びとの生活した様子がうかがえます。
弥生時代 2前田遺跡(玉名市月田)
菊池川下流の右岸自然堤防上にあります。弥生時代中期から後期にかけての竪穴住居跡が約60基確認されています。住居跡からは炭化したコメや石包丁が出土しました。周辺の土を分析したところ稲のプラントオパール(植物性のガラス質微化石)が多く含まれていることがわかりました。当時は稲作を中心とした集落が形成されていたものと思われます。また、朝鮮半島からもたらされたと考えられる板状鉄斧、石戈の転用品、北部九州地方の影響を受けた丹塗りの筒型器台、お祭りに使われたミニチュアの土器なども出土しており、川辺での生活と祭りの様子がうかがえます。
弥生時代 3東南大門遺跡(玉名市築地)
 境川右岸の段丘上にあります。弥生時代中期の墓地として使用された甕棺墓群と弥生時代の終末期から古墳時代前期にかけての遺構や遺物が見つかりました。弥生時代中期の甕棺は43基確認されており、その内の2基の甕棺内から石剣およびその先端部が見つかっています。
境川右岸の段丘上にあります。弥生時代中期の墓地として使用された甕棺墓群と弥生時代の終末期から古墳時代前期にかけての遺構や遺物が見つかりました。弥生時代中期の甕棺は43基確認されており、その内の2基の甕棺内から石剣およびその先端部が見つかっています。
 また、別の甕棺の横から、鉄剣が2本出土しており、副葬品の可能性も考えられます。弥生時代終末期から古墳時代の前期にかけては木棺墓2基、大型の溝2本が確認されています。これらは墳丘墓の可能性が考えられます。
また、別の甕棺の横から、鉄剣が2本出土しており、副葬品の可能性も考えられます。弥生時代終末期から古墳時代の前期にかけては木棺墓2基、大型の溝2本が確認されています。これらは墳丘墓の可能性が考えられます。
古墳時代 4柳町遺跡(玉名市河崎)
 菊池川下流の右岸、玉名平野中央部の水田地帯にあります。縄文時代後晩期から平安時代にかけての遺跡であることがわかりました。古墳時代前期の集落跡からは、住居跡や井戸などがみつかっています。井戸跡からは木製の短甲や道具、建物の部材、多量の土器が出土しており、これらは井戸にまつわるお祀りを行った跡ではないかと思われます。
菊池川下流の右岸、玉名平野中央部の水田地帯にあります。縄文時代後晩期から平安時代にかけての遺跡であることがわかりました。古墳時代前期の集落跡からは、住居跡や井戸などがみつかっています。井戸跡からは木製の短甲や道具、建物の部材、多量の土器が出土しており、これらは井戸にまつわるお祀りを行った跡ではないかと思われます。
 集落周辺の湿地では、土の分析の結果、稲の花粉が多く含まれていることがわかり、稲の栽培が行われていたと考えられます。
集落周辺の湿地では、土の分析の結果、稲の花粉が多く含まれていることがわかり、稲の栽培が行われていたと考えられます。
古墳時代 5城ヶ辻古墳群(玉名市寺田)
北西に菊池川を望む、見晴らしの良い丘陵の先端に位置する古墳群です。これまで5基の古墳が確認されていましたが、新たに2基の円墳が発見され、4世紀に造られた2号墳から、6世紀の6号墳・7号墳にいたるまでの長い間、連綿と続く古墳群であるとみられています。これほど長期間続く古墳群は、あまり確認されていません。新たに発見された6号墳は、熊本県地域の特色を持つ横穴式石室の跡が確認されました。これに対し7号墳の石室は、北部九州に多い「竪穴系横口式石室」と呼ばれる石室です。県内では例が少なく、北部九州との深いつながりが認められます。また、6号墳からは金製の垂飾付耳飾の一部が出土しています。垂飾付耳飾の出土例は、県内では玉名市周辺に集中しており、この地域と朝鮮半島との交流も考えられます。
古代 6立願寺廃寺(玉名市立願寺)
 昭和29年の発掘調査で礎石が確認されており、瓦の散布状況などから、法起寺式とよばれる建物の配置をもつ寺院跡と推定されています。大字立願寺にあることから「立願寺廃寺」と名付けられました。
昭和29年の発掘調査で礎石が確認されており、瓦の散布状況などから、法起寺式とよばれる建物の配置をもつ寺院跡と推定されています。大字立願寺にあることから「立願寺廃寺」と名付けられました。
 平成2年の発掘調査では、礎石建物や掘立柱建物などが確認されています。宅地化が進んでおり、平成12年に確認調査、平成13年度には道路工事に伴う発掘調査を行っています。その際に、寺院の建物跡と見られる柱穴が確認されているほか、丁寧な加工をほどこした礎石や大量の瓦、土器、硯なども出土しています。
平成2年の発掘調査では、礎石建物や掘立柱建物などが確認されています。宅地化が進んでおり、平成12年に確認調査、平成13年度には道路工事に伴う発掘調査を行っています。その際に、寺院の建物跡と見られる柱穴が確認されているほか、丁寧な加工をほどこした礎石や大量の瓦、土器、硯なども出土しています。
古代 7玉名郡倉跡推定地(玉名市立願寺)
 疋野神社北側の台地上にあり、一部が玉名市の指定史跡になっています。昭和31年の発掘調査で、柱の土台である礎石群が見つかり、炭化した米が出土することなどから、郡倉跡と推定されています。平成4年の調査では、礎石を使った建物より前の時期の掘立柱建物が確認されています。平成12年・14年には、平成4年に調査を行った地点の隣接地を調査し、規則的に並んだ建物跡を確認しています。見つかった柱穴は、直径が1mから1.5mもある立派なもので、柱穴の配置からいずれも米倉と考えられます。
疋野神社北側の台地上にあり、一部が玉名市の指定史跡になっています。昭和31年の発掘調査で、柱の土台である礎石群が見つかり、炭化した米が出土することなどから、郡倉跡と推定されています。平成4年の調査では、礎石を使った建物より前の時期の掘立柱建物が確認されています。平成12年・14年には、平成4年に調査を行った地点の隣接地を調査し、規則的に並んだ建物跡を確認しています。見つかった柱穴は、直径が1mから1.5mもある立派なもので、柱穴の配置からいずれも米倉と考えられます。
中世 8蓮華遺跡(玉名市築地)
 現在の蓮華院誕生寺を中心とした範囲の遺跡で、元は鎌倉時代中頃に建てられた蓮華院浄光寺という真言律宗の寺がありました。寺域は南北300メートル、東西200メートルにもおよび、当時の玉名地方でも有数の寺だったといわれていますが、戦国時代に消失してしまったようです。これまで数回発掘調査が行われてきましたが、平成11年度から12年度にかけての調査で、溝状遺構や土坑墓などが見つかり、寺に関連するものの可能性があります。
現在の蓮華院誕生寺を中心とした範囲の遺跡で、元は鎌倉時代中頃に建てられた蓮華院浄光寺という真言律宗の寺がありました。寺域は南北300メートル、東西200メートルにもおよび、当時の玉名地方でも有数の寺だったといわれていますが、戦国時代に消失してしまったようです。これまで数回発掘調査が行われてきましたが、平成11年度から12年度にかけての調査で、溝状遺構や土坑墓などが見つかり、寺に関連するものの可能性があります。
中世 9岩崎城跡(玉名市岩崎)
 台地上にあり、鎌倉時代から室町時代のものです。伝説では、城主が岩崎氏であったといわれています。岩崎氏については、鎌倉時代後期、中国大陸の元が九州に攻めてきた元寇の際に玉名地方から参加した武士の中に「大野岩崎太郎」の名前があり、このときの功績により恩賞を受けたことが記録されています。現在の岩崎城跡は、宅地になって家が建ち並んでおり、城の面影はほとんど残っていませんが、発掘調査によって城の周りを囲んでいた二重の堀と土塁が確認されました。この地点は、城の最も西側の部分だったようです。
台地上にあり、鎌倉時代から室町時代のものです。伝説では、城主が岩崎氏であったといわれています。岩崎氏については、鎌倉時代後期、中国大陸の元が九州に攻めてきた元寇の際に玉名地方から参加した武士の中に「大野岩崎太郎」の名前があり、このときの功績により恩賞を受けたことが記録されています。現在の岩崎城跡は、宅地になって家が建ち並んでおり、城の面影はほとんど残っていませんが、発掘調査によって城の周りを囲んでいた二重の堀と土塁が確認されました。この地点は、城の最も西側の部分だったようです。
中世 10吉丸前遺跡(玉名市寺田)
 菊池川左岸の台地上に、南北270メートル、東西150メートルのおおきな「日」の形をした空堀があったようです。鎌倉時代から室町時代にかけては、全国各地に堀で守られた城館がたくさんつくられており、この遺跡の空堀も、有力者の城を囲んでいたのかもしれません。
菊池川左岸の台地上に、南北270メートル、東西150メートルのおおきな「日」の形をした空堀があったようです。鎌倉時代から室町時代にかけては、全国各地に堀で守られた城館がたくさんつくられており、この遺跡の空堀も、有力者の城を囲んでいたのかもしれません。
 堀の中からは、食器の碗、貯蔵用の甕、調理具のすり鉢、釜などの生活道具が出土しています。また、堀の近くでは、お墓(土葬)が2基見つかりました。お墓には、小皿と坏が納められていました。
堀の中からは、食器の碗、貯蔵用の甕、調理具のすり鉢、釜などの生活道具が出土しています。また、堀の近くでは、お墓(土葬)が2基見つかりました。お墓には、小皿と坏が納められていました。
展示期間
平成15年11月12日(水曜日)〜平成15年12月23日(火曜日・祝日)
チラシ
※過去の企画展の為、チラシに掲載の情報の内、概要・趣旨などのみ記載しております。
カテゴリ内 他の記事
- 2025年2月26日 企画展四館連携事業「肥後島原同田貫道中」
- 2025年2月26日 開館30周年特別展「よみがえる同田貫」
- 2025年1月30日 開館30周年特別展「よみがえる同田貫」
- 2025年1月30日 企画展「国指定史跡熊本藩高瀬米蔵跡展」
- 2025年1月30日 企画展「第10回 たまな発掘速報展〜新発見...
- 2025年1月29日 企画展「弔う -玉名びとのお墓事情-」
- 2024年7月11日 明治初期・玉名の新しい風 高瀬藩展

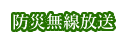






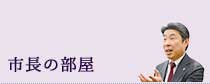
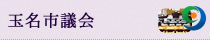
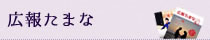
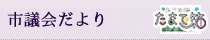
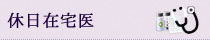

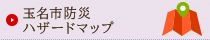
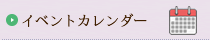
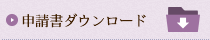
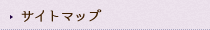
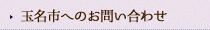
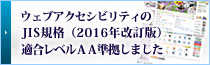
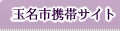

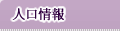

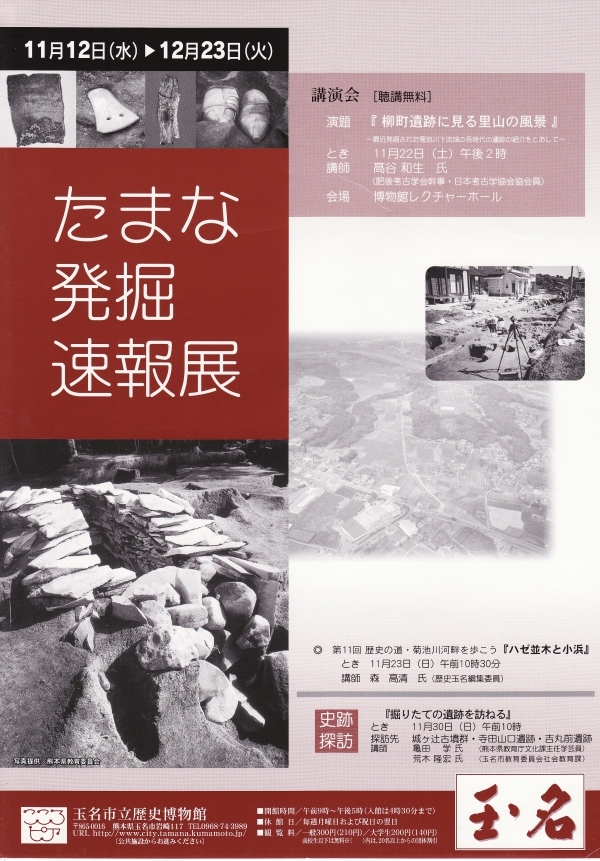
 このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。
このページは玉名市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。